
|
内の空気を真空ポンプで15分間吸引した後、注水するが、注水の際に容器内に空気を入れ 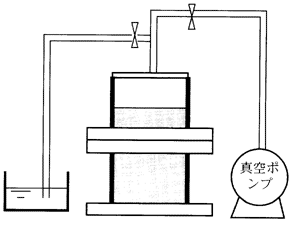
図3.4.3.3.真空引きと注水(H8) ないため、容器の蓋に水配管を接続する際には、管内を水で満たしておく必要がある。 注水の際には、水配管のバルブを開放するだけで、容器内の負圧により水が引き込まれていく。 試料の上面より約3cm程度上まで水が達したら、バルブを締めて注水を終える。試料の上まで水を注ぐのは、外気へのバルブを開けて容器内の圧力を回復させる際には、水がさらに試料の中に吸い込まれていく場合があるためである。 試料が飽和状態になったら、容器の 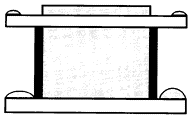
図3.4.3.4.容器の上部を外した状態(H8) 蓋と上部の筒を取り外すと、図3.4.3.4のような状態になる。試料の体積を所定の値にするため、試料は下部容器の上面に沿って切り取り、余分な試料及び水は全て除去する。 こうして所定の体積になった試料の重量を計測しておくことにより、後に、排水前の飽和度を求めることができるようになる。 (3)排水及び重量の計測 下部容器内一杯に飽和状態の試料を作成したら、参考−1−付録1の図3に示したように、適当な架台の上に試料の入った下部容器を載せ、容器底部の孔の栓を抜き、30分間排水する。排水後の試料入り下部容器の重量を計測することにより、試料の見かけ密度が求まる。 (4)水分値の計測 排水後の試料の水分値を計測する際には、下部容器の中の試料を全てバットに移して重量を計測することが望ましい。そのためには、乾燥状態のペーパータオルを用意しておき、その重量は空のバット重量に含めておく。そしてこのペーパータオルを用いて、下部容器内の試料をバットに移し、このペーパータオルと試料が入ったバットの重量を計測しておき、さらにペーパータオルも試料と共に乾燥してその重量を計ることにより、試料の殆ど全てを用いた場合の水分値を容易に計測することができる。 (5)飽和度等各種パラメータの解析 液状化物質判別試験により、直接求められるパラメータは以下の通りである。但し、真密度は予め求められているものとし、試料の重量は質量に置き換えるものとする。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|